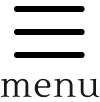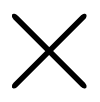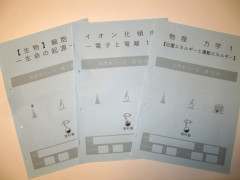コース案内
国語専科コース
論理的視点から国語を科学する。
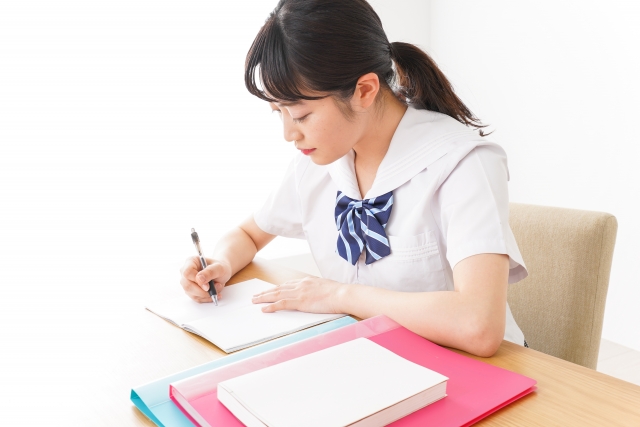
国語はすべての教科の礎であるにもかかわらず、英数の脇に追いやられがちな教科です。
一般的な学習塾では読解問題を解き、答え合わせと設問ごとの解説に終始します。また巷にあふれる問題集もその解説は不十分であったり腑に落ちなかったりします。
「雰囲気で文章を読んで解いている。」
「数学のような法則も英語のような構文もないため、勉強の仕方が分からない。」
このように国語の学習をとらえていませんか。
論説文は論理的に構成されており、小説文は心情変化をつかむポイントがあります。古文は文法に沿った分解が可能です。また小論文は分かりやすい文の法則と論の組み立て方があります。
理科塾の国語専科では国語を論理的な視点で捉えます。現代文読解では根拠に基づいた再現性のある解答を導けるように、古文では論理解釈の方法を身につけられるように、小論文では説得力のある論を展開できるように鍛錬していきます。
国語力を磨けば、思考力を向上させられることはもちろん、言葉を操る楽しさにも気づけます。
【受講の流れ】
①カウンセリング・・・簡単な確認テストを行い、問題点を洗い出します。
【国語力を向上させる指導ステップ】
STEP1 「なんとなく読む」から「論理に基づいて読む」へ
国語は、すべての教科の基礎となります。問題文を読めなければ解答も書けませんから、まずは読解力を重点的に指導します。いきなり長い文章を扱わず、基礎文法と一文の構造分解を徹底的に学んでいきます。
STEP2 文章のまとまりを捉える
一文の構造分解ができるようになったら、複数文や小段落について論理的な手法を使って要約する技術を身につけます。題材は、説明文・意見文などの文章を用います。
STEP3 論理展開を分析する
説明文や意見文には、対比・因果・例示・主張が論理的に構成されています。図解法を用いながら情報を単純化して段落ごとの関係を分析する技術を学びます。また、物語・小説などの心情変化を読み解く方法も習得します。実際の受験問題も演習していきます。
身のまわりに溢れる物や場所を文章で説明するのは、簡単なようで技術を要します。読む人とイメージを共有できるように、主観を排して客観的に分かりやすく情報を伝える技術を習得します。
STEP5 小論文を書く
課題に対して求められた視点から論を書くトレーニングを行います。根拠に基づき説得力のある意見を展開する技術を身につけます。
STEP6 古文に強くなる
日本語でありながら異文化の言語のように感じられる古文は多くの中高生に苦手とされやすい分野です。古文を読み下すには、外国語を学ぶときと同様に知識と技術を習得する必要があります。また、いにしえの人々の風流や心の機微を知ることは、現代に生きる私たちへの気づきや教訓になります。
【時間】火ー土(週1コマ 100分/コマ 曜日時間は面談後決定)
【受講スタイル】個別指導+演習添削
【対象】中高生
英数との並行受講がおすすめ
中高一貫校コース
大学受験を見据えて学ぶ

中高一貫校に通う中高生対象のコースです。
大学受験を目指す中高一貫校では、入学からの2年間で中学の範囲を履修します。特に数学・英語は大学受験を見据えた体系と進度で行われます。
また大学附属系中高一貫校では、大学受験に特化した授業は行われないものの、内部進学の希望を叶えるために校内の成績を上位に維持しなければなりません。
理科塾では、プログレスや体系数学を用いて論理的メソッドを用いた単元指導を行います。
内部進学および大学受験を見据えることはもちろんのこと、行間を探り原理法則の裏側まで考えられる力の習得を目指します。
受講プラン
【プラン例1 ついていけなくなった教科の立て直しを図りたい】
【プラン例2 学内の成績を上位で維持したい】
【プラン例3 大学受験を見据えた学習を始めたい】
【時間】火―土 (週1コマ~ 100分/コマ 曜日時間は面談後決定)
【受講スタイル】個別指導+演習添削
【対象】中高一貫校に通う中学1年生以上
【教材】プログレスや体系数学を中心に、個別プランに添ってテキストを決定します。(別途テキスト代あり)
受験英数コース
論理メソッドで難関校を目指す。
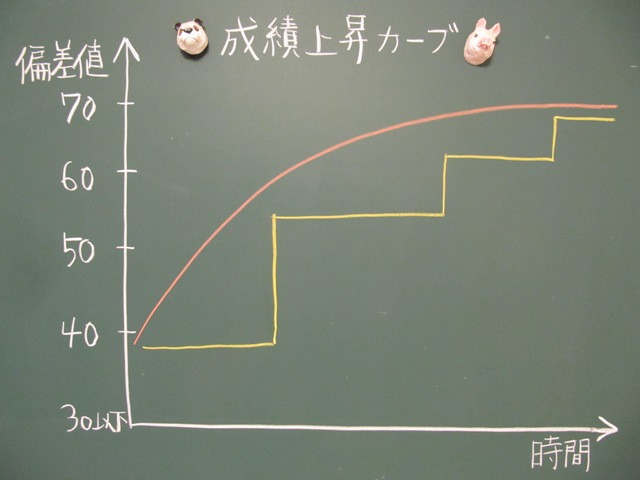
解き方に終始するだけの指導ではなく、教科との正しい向き合い方を指南します。
▼合格体験記はコチラ
理科実験塾として培った論理的なメソッドを用いて数学・英語の学力向上を目指します。例えば数学は、計算力のみを鍛えれば良い教科と思われがちですが、解答に至るまでの筋道を考える力が必要とされる教科です。
英語
また日本語と言い回しの異なる英語表現は、英単語を単純暗記する方法で対処できません。語句のはたらきと意味を理解して、重要構文の引き出しを増やしましょう。
数学
オリジナルプリント&チャート式問題集を繰り返しながら、解法の引き出しを増やし、情報の整理の仕方とノートへの書き出し方を学びます。
【プラン例① 学習習慣の定着と受験に向けた基礎力向上を目指す中学1・2年生】
【時間】火―土(週1コマ~ 100分/コマ 曜日時間は面談後決定)
【受講スタイル】個別指導+演習添削
【対象】中学生および高校生
【教材】個別プランに添ってテキストを決定します。(別途テキスト代あり)
▼理科塾的勉強のコツを披露しています。
探究実験コース
探究する理科実験で理系脳を育む。

科学の原理を知り、理系力を鍛える
森羅万象は自然科学に通じます。知識と経験が日常の中に潜む科学と結びつく時、学びは生きた力となります。科学現象の原理を探究する中で科学の本質と意味を知れば、論理力と応用力が鍛えられます。
【テーマ】
化学・物理・生物(解剖も含む)・地学
年間カリキュラムに沿って進みます。
1つのテーマを数回に渡り、丁寧に深く掘り下げます。
オリジナルテキストに記録と考察をまとめながら学習します。
【実習の流れ】
安全に十分に配慮した上で、生徒が主体となって実験に取り組みます。
講師の演示実験を観て終わりではありません。超少人数制だからこそ実現できる実習があります。
STEP1 実験の計画
必要な知識を習得して、今日の課題を理解してから実験に臨みます。
STEP2 準備と進行
安全への配慮はもちろん、正確かつスムースな進行に向けての環境を考えましょう。
STEP3 記録方法の検討と検証
実験結果を左右する測定方法と実験条件を検討しましょう。
STEP4 新たな疑問に対する考察
仮説と異なる結果に対する考察を深めましょう。
▼実験の画像とコメントをご覧いただけます。


| 【内容】 | 化学・物理・生物(解剖も含む)を中心にした体系的カリキュラムを用意しています。仮説の立て方・実験計画の練り方を学び、失敗や途中で沸いた疑問に対する再検証も時間の許す限り行います。 |
| 【レベル】 | 中学から高校の学習範囲に加えて、教科書には載っていない発展的内容にも踏み込みます。実験を行うことでしか学べない実習ノウハウも身につけます。 |
| 【対象】 | 中学1年生以上~ 理系に興味がある方・理系の進学を考えている方 お楽しみ理科実験や学校の理科に物足りなさを感じる方 |
| 【時間】 | 1回150分×2コマ/月 |
| 【定員】 | 1~4名 |
▼理科実験で育まれる学力とは―探究活動が注目されるわけ―